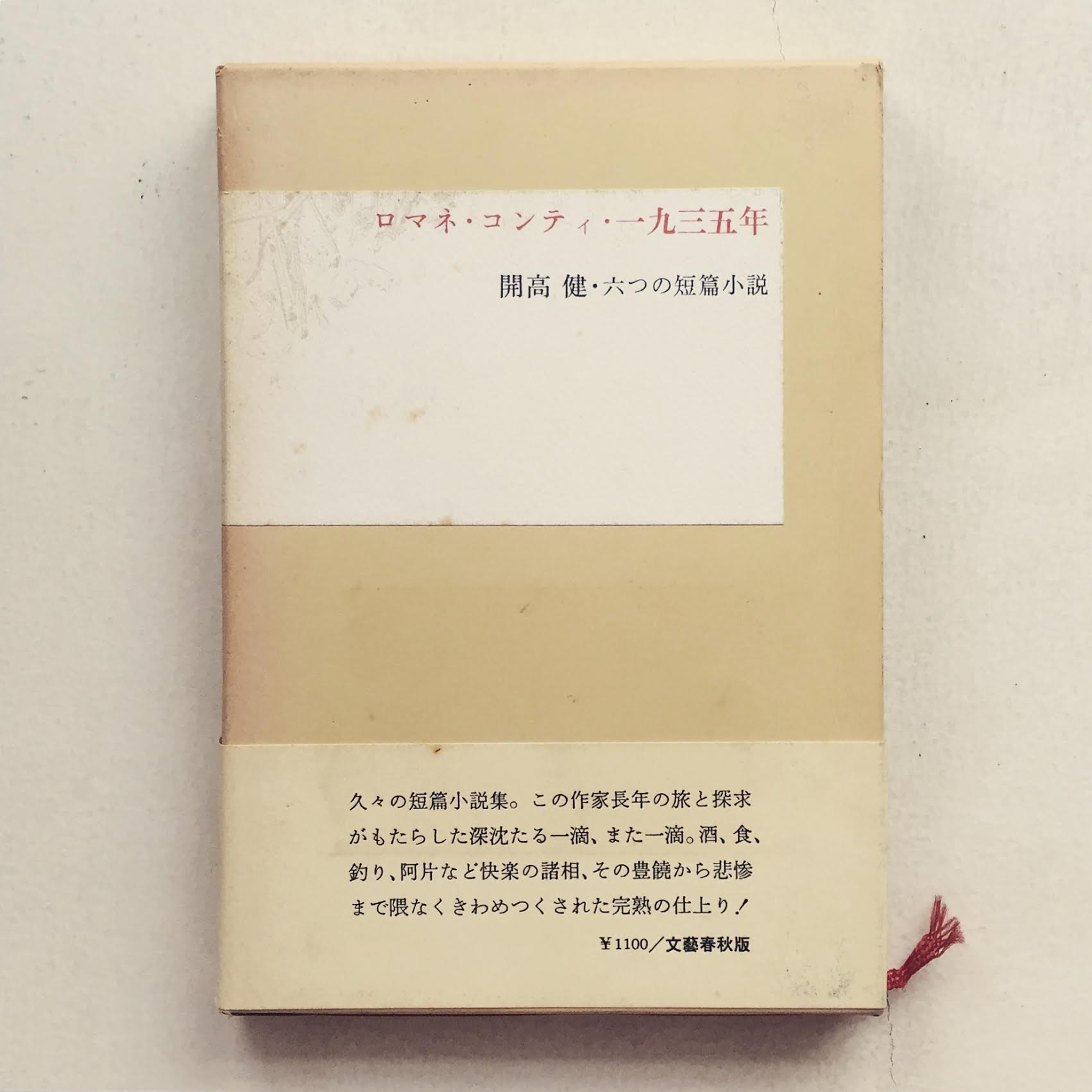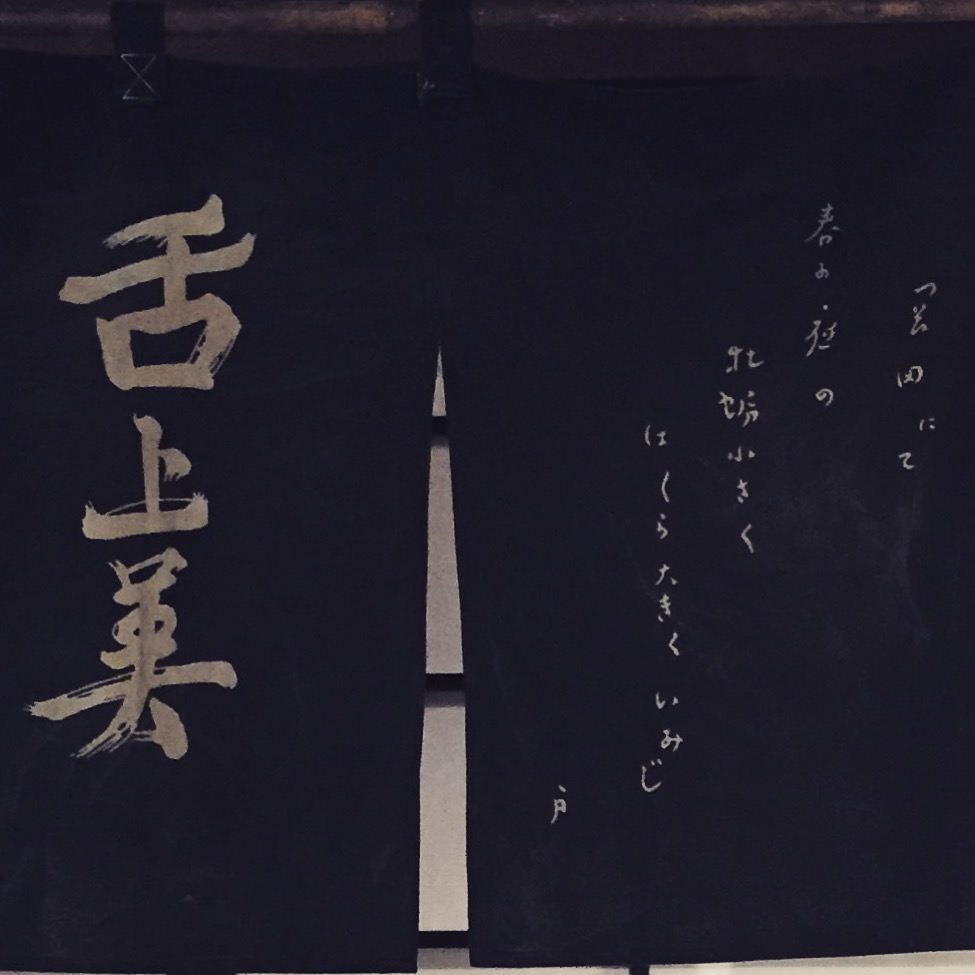酒と記憶。
正体を失うほど酔っ払った、いわゆる「へべれけ」の人を酒場で見かけることが、ほとんどなくなった。落語や映画で描写される、呂律がまわらなくなった人物。たとえば小津安二郎の映画に出てくる東野英治郎みたいな酔客。そういう人がたくさん居るかもしれない酒場に、自分が出入りしていないだけなのだろうか。そういえば「へべれけ」という言葉もあまり耳にしない。「メートルが上がる」みたいな、酒にまつわる他の表現と同じように、なにか面白い語源があるのじゃないかと思いちょっと調べてみたら、語源はギリシャ語だという説を唱えているものが多かった。元は「ヘーベ・エリューケ」。へーべはゼウスとヘラの間に生まれた女神で、酒を勧めるのが上手なので、神々たちが宴でつい飲み過ぎて酔ってしまうのだという。エリューケはお酌。まるでヘーベにお酌をされたように適量を超えてしまった状態を表す言葉を、短縮した日本語が「へべれけ」なのだそうだが、そのまま鵜呑みにはできない胡散臭さが漂っている。
小津映画における東野英治郎の酔っ払い演技で好きなのは『お早う』(1959年)だ。自分の家のつもりで入った近所の家の玄関口でのコント。それからもうひとつ、アンリ・サルヴァドールのはじめての日本公演で(この時、アンリはすでに85歳だった)彼が披露したスケッチ。生放送のジンのTVコマーシャルに出演する男が、回を追うごとに試しに飲んでみせるジンの摂取量が増え、ベロベロになっていくというもの。酔っ払いを演じるのに、洋の東西はないのだなと思いながら大笑いした。
ぼくはずっと、酒を飲み過ぎて記憶がないという話を誰かがすると、きっとバツが悪いからそういうふうに言っているだけなのだろうと聞き流していたが、数年前に、それが本当に起こるということを初体験した。ひとりにつきワインをボトル1本ずつ頼むことという厳しいルールの店に行った時だ。酒豪の女性2人と一緒だったから問題ないと思っていたのに、頼みの2人がこの後で原稿を書くからなどと言って、まるで別人のようにちびちびとしか飲まない。そしてどんどんぼくのグラスにワインを、ヘーベのごとく注ぐのだ。3時間ほどしてからだろうか、会計を済ませて店を出た。駅まで続く坂道を上っていく。次の瞬間、ぼくは自宅のベッドに横になっていた。きちんと着替えている。でも、店を出てからのことを何も憶えていない。カミさんに尋ねると駅からラインが来たと言い、「かなり上機嫌で帰ってきたけどね」と付け加えた。自分の携帯を確かめる。「いま乗換えの電車を待っているよ」というテキストだけでなく、ご丁寧にスタンプまで送っていた。
それからしばらくしたある日、前に使っていた携帯に入れたままの写真を整理している時に、撮ったおぼえのないものが何枚かあることに気付いた。一緒に飲んだ人たちとの記念写真のようだった。どれもやたら弾けた表情だ。ぼくは急に怖くなった。いままで酒で記憶を失ったことはないと思っていたが、前後が繋がっているから自分ではそう考えているだけで、もしかしたら何度もそんな失態があったのかもしれない。
(2019年3月30日)